2023年の米国経済の動向と2024年の見通し
軟着陸期待高まるが、業種間のバラつきや不確実性も
2024年3月11日
2022年秋ごろから2023年前半にかけて、多くの民間調査機関は、高インフレと連邦準備制度理事会(FRB)の金融引き締めなどに伴う高金利の影響により、米国経済は2023年中に景気後退に陥ると予測した。しかしながら、実際には2023年の成長率は2.5%と、潜在成長率とされる1.8%を大きく上回る成長を見せた。予想以上の成長は何が要因だったのか。その理由を検証するとともに、これを踏まえた2024年の米国経済について展望していきたい。
2023年における米国経済の動向
まず、実質GDP成長率を見ると、2023年前半は消費および設備投資に牽引されて前期比年率2%を超える成長を見せ、後半は旺盛な消費に支えられて、第3四半期は4.9%、第4四半期も3.2%(改定値)と高い伸びになった(図1参照)。2023年通年では前年比2.5%と、潜在成長率である1.8%を大きく上回る結果となった。
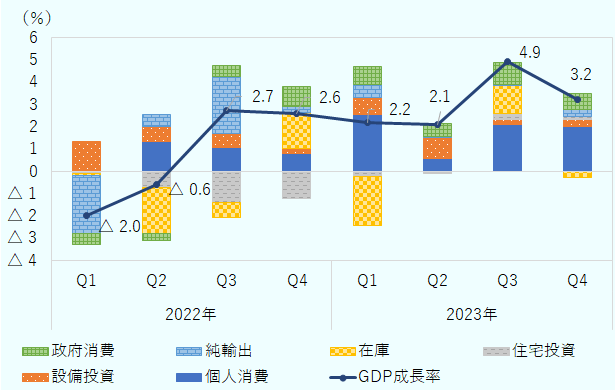
出所:米商務省
しかしながら、民間経済予測Blue Chip Economic Indicatorでは、2022年10月から2023年2月にかけて、高インフレに伴う消費意欲の減退や、FRBによる金融引き締めに伴う設備投資の下押しなどを見込み、2023年前半の小幅のリセッションを予想していた(表1参照)。最も落ち込み幅が大きかった2023年1月時点の予測を基に主な需要項目を見ると、消費・設備投資ともに予測と実績値が大きく乖離したことがわかる。
| 項目 | 2023年Q1 | 2023年Q2 | 2023年Q3 | 2023年Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 成長率 | △0.5(2.2) | △0.9(2.1) | 0.0(4.9) | 0.9 (3.2) |
| 消費 | 0.4(3.8) | △0.4(0.8) | 0.0(3.1) | 0.6 (3.0) |
| 設備投資 | △0.4(5.7) | △1.8(7.4) | △1.0(1.4) | 0.3 (2.4) |
| 失業率 | 3.9(3.5) | 4.3(3.6) | 4.6(3.7) | 4.8 (3.7) |
出所:Blue Chip Economic Indicator
予想以上の成長となった理由
では、こうした想定以上の成長は、なぜ実現したのだろうか。(1)想定以上に良好な家計状況、(2)金利の引き上げが効きにくい環境の2つが主たる要因と考えられる。
まず、1つ目の良好な家計状況について見ていこう。家計は、ストック(余剰貯蓄)とフロー(賃金)両面ともに比較的良好に推移したといえる。
ストック面については、新型コロナウイルス(以下、コロナ)禍での行動抑制や財政支出(教育ローンの返済猶予、各種給付金など)によって、ピーク時には余剰貯蓄として2兆3,000億ドル程度積み上がった、と推計されている(2023年1月10日付地域・分析レポート参照)。2022年の後半以降、これが消費者に安心感を与えるとともに、高インフレへのバッファーとなってきた。2023年の中ごろのどこかで尽きると想定されていたこの効果が、(a)夏場やホリデーシーズンなどに見られたEコマースや大手小売事業者の大規模な値引きセールなどの販売強化戦略、(b)トレードダウン(低価格帯へのシフト)と呼ばれる消費者の行動変容、(c)想定以上に堅調な米景気を受けた金融資産の価値上昇などを理由として、良好な家計状況が当初予想されていたよりも長く続いたとみられる。
次にフロー面については、労働需要の逼迫に伴い、賃金上昇率は2023年中もコロナ前のトレンド(2~3%程度)を上回る4%台で推移した(図2参照)。労働市場に関しては、先述のBlue Chip Economic Indicatorでは、失業率が第2四半期以降は自然失業率である4.0%を超え、2023年内に4.8%まで上昇すると予想されていたが、実際には2024年1月時点でも3.7%と、大きく乖離している。予想と乖離した理由には、需給両面でさまざまな理由が考えられる。需要面は、(a)サプライチェーン混乱の落ち着きに伴い製造業や運輸業などの労働需要が特に年の初めごろに強く出たこと、(b)レストランなどの娯楽・接客サービス分野などにおけるペントアップ需要(繰り越し需要)が夏場やホリデーシーズンなどに予想以上に盛り上がったこと、(c)インフラ投資雇用法(IIJA)をはじめとするバイデン政権による各種施策の効果により、建設業などにおいて労働需要が金融政策とは無関係に増加したこと、などの要因が相互に関連し合い、2023年を通じて比較的強く保たれたのではないかと考えられる。
供給側では、特に早期リタイアした高齢者層や若年層などで労働参加率が低く抑えられたこと、移民労働力がコロナ前の水準を回復するのになお時間を要したことなどが要因として挙げられる。こうした結果、売り手有利な環境が続き、賃金上昇が継続した模様だ。
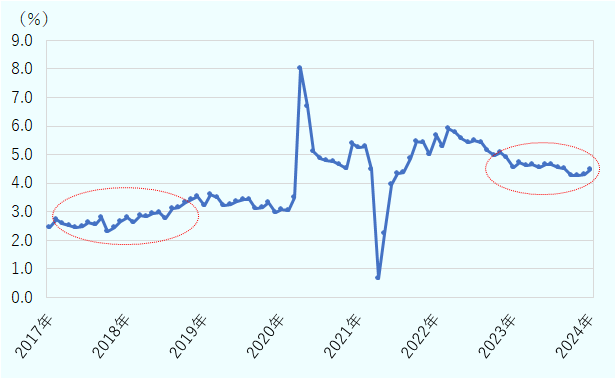
出所:米労働省
続いて、金利の引き上げが効きにくい環境という2つ目の理由について見ていこう。家計部門でそれが最もよく表れたのが住宅市場だ。コロナ禍でのライフスタイルの変化も相まって郊外などへの住み替えを求めて、2021年から2022年にかけて住宅需要は急速に高まり、その際、多くの人が30年固定ローンを組んで住み替えを行ったといわれている。このため、新たに住み替えを行わない限りは、その後の金利引き上げによる影響が家計に及びにくい状況にあった。また、企業部門も同様に社債の借り換えを行い、必要な手元資金を確保したことから、償還が比較的少なかった2023年は設備投資や雇用などに影響が及びにくい環境にあった。これに加えて、インフレ削減法(IRA)やCHIPSおよび科学法(CHIPSプラス法)などによる支援の効果もあり、製造業における設備投資は年間を通じて大きな伸びを続けるなど、バイデン政権による支援策が企業の設備投資意欲を刺激した模様だ(図3参照)。
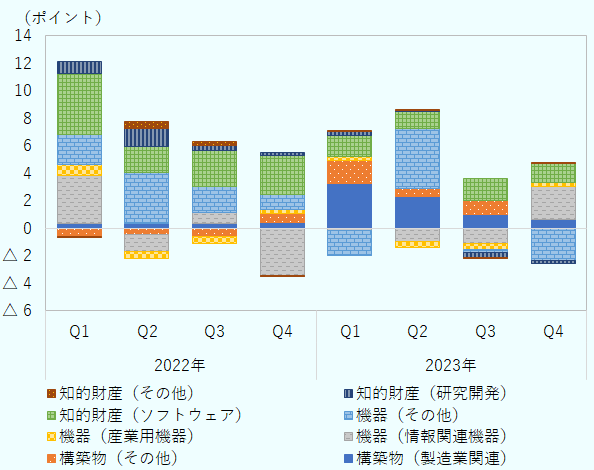
出所:米商務省
これらの要因は続くか:家計状況と今後の展望
では、こうした要因は持続するのだろうか。まず、家計状況から見ていこう。余剰貯蓄が現在どの程度残っているのかについては、さまざまな議論が存在する。サンフランシスコ連銀は、2023年12月時点で依然として2,000億ドルが残っている可能性を示唆する一方、11月の米地区連銀報告では、カンザスシティ連銀から「低・中所得者層が貯蓄をほとんど使い果たしており、家計をやりくりするためにますますクレジットカードに頼るようになっている」といった報告がされる(2023年12月1日付ビジネス短信参照)など、いくつかの地区連銀からは低・中所得者層の余剰貯蓄は既に尽きつつあるといった見方が出ていた。額には幅があるものの、消費行動に影響を及ぼす程度に減少していることは間違いないようだ。クレジットカードローンのローン残高は過去最高値を更新し続けるとともに、事実上の債務不履行である90日以上延滞率は急速に上昇し、2011年以来の高水準となっている(図4参照)。また、年末商戦においても、後払い決済〔バイナウ・ペイレイター(BNPL)〕サービス利用者が前年同期比で14%増と大幅に増加するなど、支払いを先延ばしにする傾向が見られている。これらにみられるような、家計の財務状況の悪化については、2024年1月の連邦公開市場委員会(FOMC)においても、一部の理事から今後の消費の下振れリスクとして指摘されている。これに加え、消費者がクレジットカードローンなどへの依存を高める一方で、FRBの調査(SLOOS)では、多くの銀行がクレジットカードや自動車ローンの融資基準を2024年にかけてさらに厳格化すると回答しており、現在の消費行動の持続性には疑問が残るところだ。さらに、家計負債の約10%を占める教育ローンの返済免除が終了し、1人あたり月平均503ドルといわれている返済が2023年10月から再開している。これも貯蓄率の低下につながり得る要素となる。以上を踏まえれば、今後はストックを根拠とした消費行動は難しそうな状況だ。
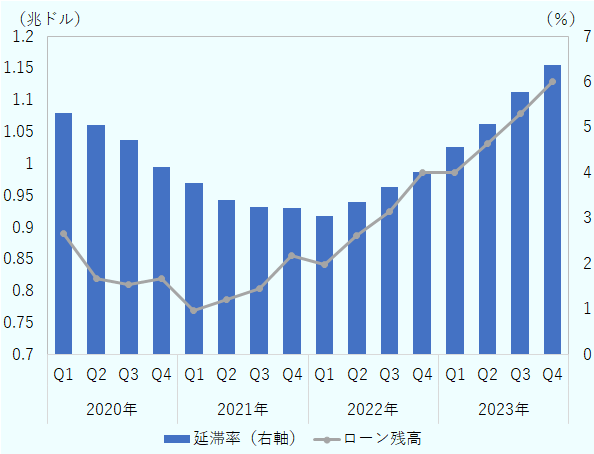
出所:ニューヨーク連銀
これらの要因は続くか:賃金および労働市場の展望
次に、フロー面を見ていこう。先に述べたように、失業率は自然失業率とされる4.0%を下回る水準で推移しているほか、おおむね月10万人から15万人程度が目安とされる非農業部門新規雇用者数についても20万人程度の水準で推移し、指標上は堅調だ(図5参照)。しかし、こうした需要の内訳をみると、恒常的に強い伸びを示しているのは、教育・医療サービスや娯楽・接客業、建設業などいわゆるブルーカラーを中心とした業種や政府部門に偏っている。このうち、政府部門や建設業、あるいは電気自動車(EV)・バッテリー・半導体関連など一部の製造業は、バイデン政権によるIRAやCHIPSプラス法などによる政策効果に強く支えられている面も大きいと考えられる。
一方、例えば金融業や情報通信業といった典型的なホワイトカラーの業種では、ほとんど伸びが見られない。チャレンジャーグレイ・クリスマスの調査によると、これらの部門では2024年に大規模な人員削減が計画されており、こうした傾向は続きそうだ。この他にも、小売業など消費に近い業種も、先に挙げた家計の財政状況の悪化に伴って裁量的支出が徐々に減少していくとの見込みから、同様に人員削減を計画しており、こちらも徐々に減速していく可能性が高そうだ。2023年には強い伸びを示していた娯楽・接客業も、同様の理由から2023年ほどの強さは期待しにくい。
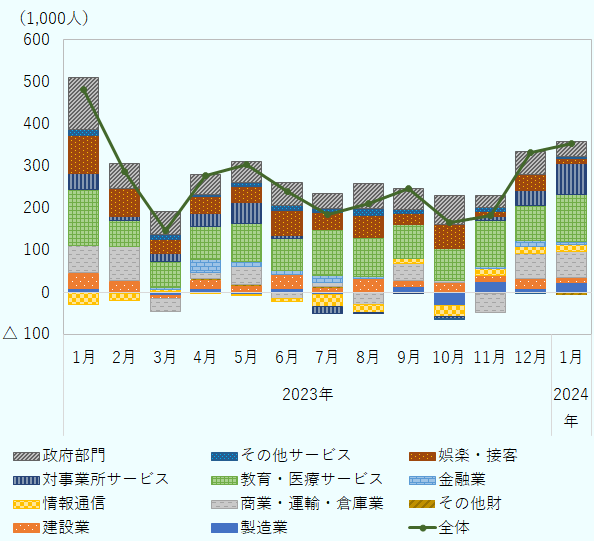
出所:米労働省
このように、全体としては堅調に見える雇用情勢も、業種によってバラつき始めており、こうした傾向は2024年にかけて継続し、全体としては、2023年よりも労働需要は緩やかに減少すると想定する。もっとも、金融政策の動向や11月の大統領選挙などに伴う財政政策の変化などにより、影響を受ける可能性もある。
他方で、労働供給については、労働参加率は2023年11月の62.8%をピークとして、その後は12月、1月ともに62.5%に低下するなど、このところやや頭打ち感がある。コロナ後の移民労働力などの回復といった、2023年のような大幅な労働供給の増加要因は見込みにくいことから、労働供給が大きく改善する可能性は低いと考えられる。また、1月はやや改善したものの、平均失業期間の長期化や、失業保険給付者総数の高止まりの傾向も見られる(図6参照)。この理由は必ずしも明らかではないが、筆者は先に挙げた労働需要の部門ごとのバラつきから、失業者の持つスキルと労働需要がマッチしていないことが要因ではないか、と考えている。仮にそうだとするならば、この傾向は比較的長期のものとなるのではないか。また、移民労働力をめぐっては、国境措置の強化が2024年度本予算における議論や大統領選の大きな争点になっている。これまで比較的移民政策に寛容な姿勢を示していたバイデン政権も、国境措置の強化にかじを切り始めるなど(2024年2月6日付ビジネス短信参照)、民主党・共和党の間で程度の差はあるものの、現在よりも国境措置を厳しくする方針自体は共通しており、移民労働力の増加幅には一定のブレーキがかかる可能性が高い。
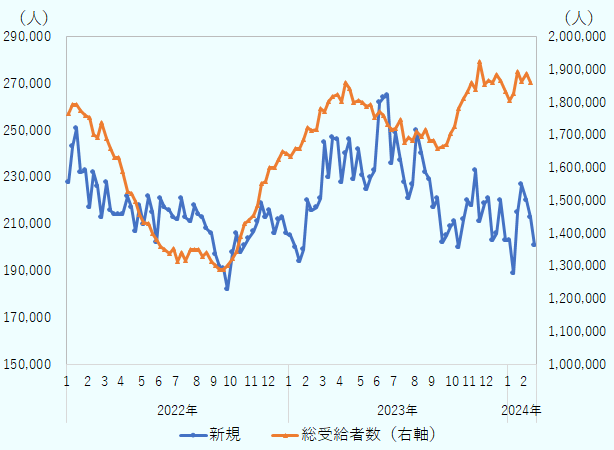
注:本統計は週次で公表されているもの。総給付者数は新規給付者数より1週間分遅れて公表される。
出所:米労働省
このように、労働需要・供給ともに下押しリスクがあると考えるが、総じていえば、労働需要の減速の方がやや強く、労働需給は引き続き緩やかに緩和していくのではないかと考える。また、この動きとあわせて、賃金上昇率は徐々に低下していくと予想する。ただし、先に見たように、ホワイトカラーでは労働需給の緩和が比較的早いペースで見込まれる業種が多く存在する一方、ブルーカラー、例えば製造業のように、政策効果による労働需要の増加が見込まれる上、自動車産業にみられるように2023年の労使協定に伴って今後数年にわたる賃金上昇が取り決められている業種もある。現在も、部門によって賃金上昇率に差異が見られている(図7参照)が、こうした傾向がさらに顕著になると考える。これに加え、賃金には一定の下方硬直性も存在するため、労働需給の緩和ペースほどには賃金上昇率は低下しないかもしれない。
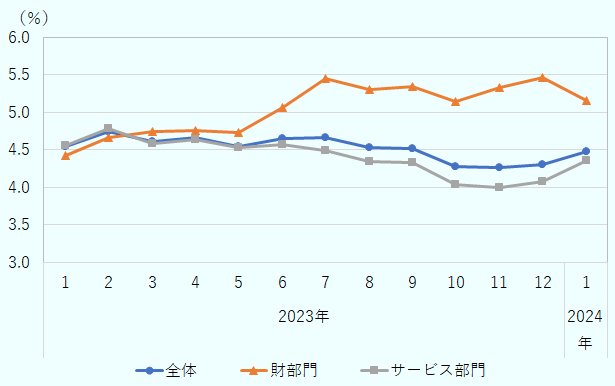
出所:米労働省
また、消費は実質賃金との相関が高いことから、物価動向にも着目すると、消費者物価指数(CPI)は2024年1月時点で前年同月比3.1%とピーク時(2022年6月:9.1%)から約3分の1に、変動の大きい食料品・エネルギーを除いたコア指数も1月は3.9%と低下してきている。財価格は既におおむねゼロ近傍であり、住居費を除くサービス価格も3.6%とピーク時(2022年9月:8.2%)から半分以下となっている(図8参照)。また、FRBが注目する個人消費支出(PCE)デフレーターについては2023年12月時点で2.6%、コア指数は2.9%と、FRBが12月時点で予想したよりも若干早いペースで低下している。
このように、全体としてインフレ率は低下してきたものの、今後どの程度のペースで低下していくのかについてはなお予断を許さない状況だ。CPIでは、コア指数はこのところ下げ止まっている感もある。先に述べたように、賃金については比較的下がりが遅い可能性が高く、これが価格に転嫁されることにより、サービス価格などは引き続き高い伸びを示す可能性がある。また、インフレ率の急速な低下を支えてきた財部門については、既にゼロ近傍で推移しており、さらなる寄与は期待しにくい状況だ。住居費はおおむね住宅価格から18カ月遅行して推移するとされており、今後の低下はこの部門のペースによることとなる可能性が高いが、瞬間風速を示す前月比では、足元の住宅価格の高止まりなどを受けて1月は前月比0.6%増と加速に転じており、そのペースは不透明だ。また、エネルギー価格については、地政学的リスクにより変動が大きい分野であり、中東情勢の推移次第ではかなり不安定な動きにもなり得る。このように、現状ではFRBが目標とする2%に向けて着実に歩を進めるのか不確定な要素が多く、しばらくは予断を持たずにデータを見ながら、そのトレンドを精査していく必要がありそうだ。
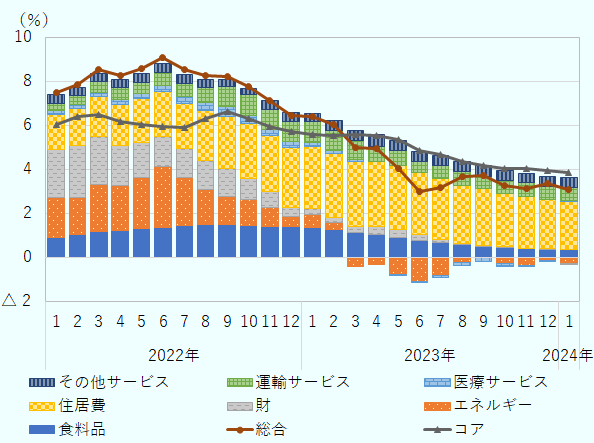
出所:米労働省
以上を踏まえて、フローに関して総じていえば、賃金上昇率およびインフレ率はともに緩やかに低下するものの、賃金上昇率の低下はより緩やかなものとなり、実質賃金はプラスで推移する可能性が高いと見込む。ただし、先に述べたように、賃金は業種によってかなりバラつきが出ると考えられることから、差異が大きくなることには留意が必要だ。
これらの要因は続くか:金利上昇の影響
金利上昇の影響についても、2024年にかけて徐々に顕在化してくると考えられる。特に、企業部門では、2024年前半からコロナ禍で調達した資金の借り換え時期を迎えるといわれており、企業の資金繰りは2023年と比較して悪化しそうだ。このため、設備投資については、人手不足や生産性向上に対応するための人工知能(AI)やソフトウエア投資や、IRAなどに後押しされた再エネ、半導体、バッテリーといった一部の製造業における機器類など、かなり選択的に行われるようになると考える。また、資金繰りの悪化に伴って、収益性が悪化した資産の売却や雇用の縮小なども想定される。
家計部門では、既に影響が出始めている。先に挙げたクレジットカードローン以外にも、自動車ローン金利(60カ月)は2022年初めの4%程度から、2023年末ごろには7.7%にまで上昇している。地区連銀からは、こうした金利の上昇の結果、ローンの長期化(60カ月→84カ月)や自動車販売の低下が見られるとの報告がされているほか、クレジットカードローンと同様に、事実上の債務不履行も急速に増加している。また、住宅については、高金利によるロックイン効果(囲い込み効果)に伴って、中古住宅を中心に住宅価格が上昇に転じ、全米ホームビルダー協会は、こうした状況が住宅販売に影響を与えていると指摘している。後述のように、FRBによる金融引き締めは少なくとも2024年前半までは続く可能性があると見られており、それまでは金利が下がりにくい環境にあることから、こうした金利高の影響は継続することになる。先に述べたように、2023年と比較すると家計におけるバッファーは大きく減少していることから、2024年には金利高が本格的に影響し始めると予想する。
金利の影響がどの程度のものとなるのかは、FRBの金融政策次第だ。12月のFOMCでは、FOMC各委員による見通しが示され、2024年の金利水準は3回分の利下げを示唆する内容となっている(表2参照)。ただし、1月のFOMCでは、「インフレ率が2%上昇に向けて持続的に推移しているとより確信が得られるまで、利下げするのは適切ではない」との見解が示され、FRBとしては、利下げを急がないスタンスのようだ。先に述べたように、インフレ率の低下スピードはかなり幅を持って見る必要があり、市場関係者の間でも、現時点では夏ごろの利下げ開始を想定する声が多い。
| 項目 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 長期 |
|---|---|---|---|---|---|
| FF金利 |
5.4 (5.6) |
4.6 (5.1) |
3.6 (3.9) |
2.9 (2.9) |
2.5 (2.5) |
| 失業率 |
3.8 (3.8) |
4.1 (4.1) |
4.1 (4.1) |
4.1 (4.0) |
4.0 (4.0) |
| インフレ率(PCE) |
2.8 (3.3) |
2.4 (2.5) |
2.1 (2.2) |
2.0 (2.0) |
2.0 (2.0) |
| インフレ率(コアPCE) |
3.2 (3.7) |
2.4 (2.6) |
2.2 (2.3) |
2.0 (2.0) |
— |
注:カッコ内は2023年9月時点の見通し。
出所:FRB
2024年はソフトランディングを基本としつつもさまざまな可能性があり得る
これまで見たように、2024年は2023年の高成長を支えた要因の多くが剥落する見込みだ。このため、現在、メインシナリオとして多くのエコノミストが予想するのは、年半ばにかけて金融引き締め効果の顕在化に伴い緩やかに景気減速しつつ、年後半から段階的な利下げなどに伴って回復軌道をとっていく。この結果、経済は2%程度の成長と前年よりは幾分減速するものの景気後退に陥ることなく、物価安定目標達成に向けた着実な道を描く。いわゆるソフトランディングと呼ばれるシナリオだ。ただし、ソフトランディングが実現するかどうかは、フロー面での堅調さがどの程度続くか、高金利の影響をどの程度緩和できるかといった点、すなわち見通しにくい状況にある物価の動向に大きく左右される、薄氷の上に立つものであることに留意が必要だ。アップサイド・ダウンサイド双方とも多様なシナリオがあり得ることを想定しておきたい。また、本稿で取り上げた事項以外にも、商業用不動産をめぐる状況や大統領選に伴う政策効果の剥落・変更などいくつかのリスクも存在しており、引き続き動向を追っていく必要がある。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ ニューヨーク事務所 調査担当ディレクター
加藤 翔一(かとう しょういち) - 2009年、内閣府入府。骨太の方針の策定や世界経済の分析、子育て支援に従事したほか、内閣官房や農林水産省、消費者庁などに出向し、地方活性化に向けた施策等を担当。2023年7月から現職。




 閉じる
閉じる






